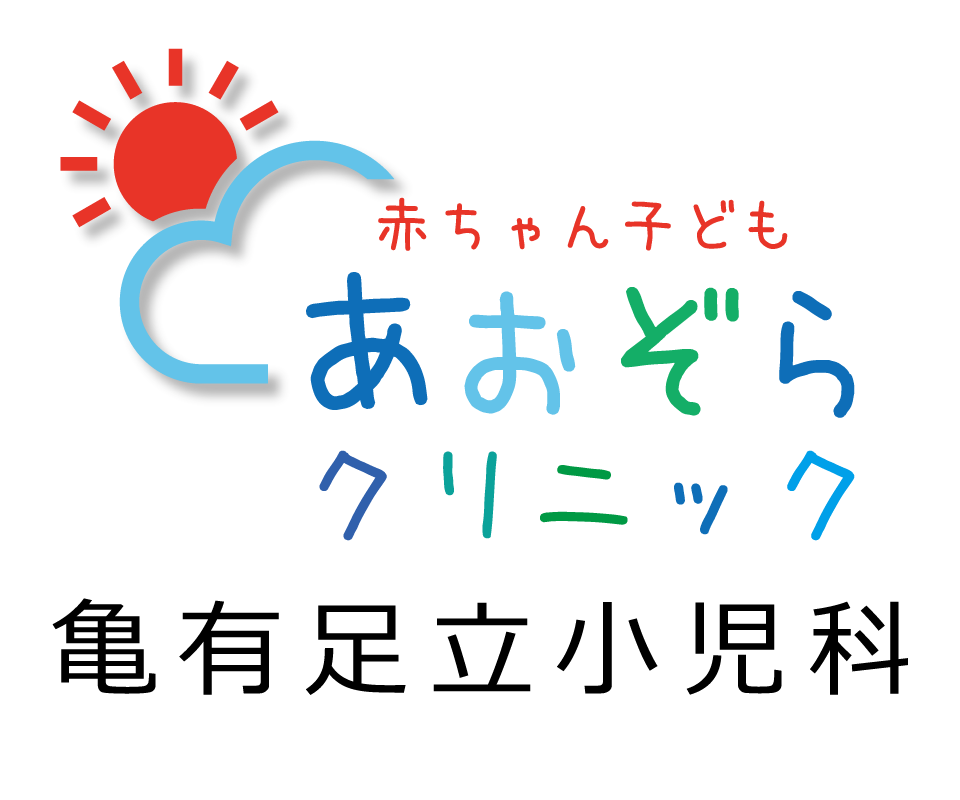はやり目はやってる!?
こんばんは。
首、肩の痛みがひどくて困っている院長岡田です。
月曜日は朝からホントにひどくて、左が向けない状態でした。
流石につらかったので、火曜日の夜にマッサージしてもらったんですが、「こりゃ結構ひどいですね…」って言われました。
それからはずっとロキソニンシップ張りっぱなしの生活です。
ちょっと動くようになってきましたが、まだまだ痛いです。
先週の土曜日は2回目のかかりつけ患者専用インフルエンザワクチン接種を行いました。
1回目の教訓から、受付時間を早くして短くしました。周知期間が長かったことも関係しているかと思いますが、
結果、1回目の2倍くらいの方が来られました。
長くお待たせした方も多かったかと思います。
それでも、「来年もやっていただけると助かります」という感想をいただきました。
来年はまたやり方を考えてやっていきたいと思います。
さて、相変わらず手足口病が多いです。
熱と咳が続くお子さんにはマイコプラズマが多いです。
そのため、マイコプラズマの検査キットがかなり不足してきています。現状、キットの注文はしていますが当院には在庫がない状態です。
最近気になるのが、「はやり目」です。
一部保育園、幼稚園で発生しているようです。
正式名称は、「流行性角結膜炎」で、原因はアデノウイルスです。
目が赤くなり腫れて、目やにが出て、かなり痛いです。
かなり感染力が強いため、
「眼科の先生から許可が出るまで出席停止」
という強烈な感染症です。
今までも保育園ではやり目が流行ってる、
ということが以前にもありましたが、正直僕の見た感じでは違いそう、ということが多かったです。
ところが今回は、「ん!? はやり目っぽいぞ」というお子さんがちらほらいらっしゃいます。
実は僕自身、このクリニックを開業する年の1月にかかりました。
目を開けていても、閉じていても痛くて、本当にきつかったです。
当時勤めていたクリニックを、10日間くらい休診にしました。正直、診察どころではなくて、生活困難な状態でした。
僕の後、妻と子供たちもかかりました。
そして、僕がお世話になった眼科の先生も、「お前のせいで俺もかかったよ」という感じで、眼科の先生にもうつしてしまいました。
今日、北三谷小学校の就学時健診が午後ありました。
その時に、眼科の朝蔭先生にお聞きしたところ、
朝蔭先生が診察された、保育園ではやり目が流行っているということで受診した3名のお子さんは、みなさんはやり目ではなかった、
ということでした。
僕が診察したお子さんと一緒かどうかがわからないので何とも言えませんが、
実際にはそんなに流行っていないのかも!?
今後も注意してみていきたいと思います。